津軽金山焼
津軽の土と赤松の炎が育てた、釉薬を使わない焼締陶器。水をきれいにする器づくり。
津軽金山焼は、青森県五所川原市・金山の大溜池に堆積した粘土と、風雪に耐えてきた山林の赤松を用い、釉薬を一切使わずにおよそ1300〜1350度の高温でじっくり焼き締めた陶器です。土と薪の力だけで生まれる深い色合いや窯変、焼き締めならではの通気性の良さから、「水をきれいにする力」をもつ器としても知られています。ギャラリー和土WANDOでは、普段使いのうつわからギフト、インテリア、ピザ窯まで幅広い作品が並び、敷地内のレストラン「山の風」では金山焼の器で食事を楽しむこともできます。津軽の風土に根差した土と炎の工芸を、暮らしのすぐそばで味わえる窯元です。
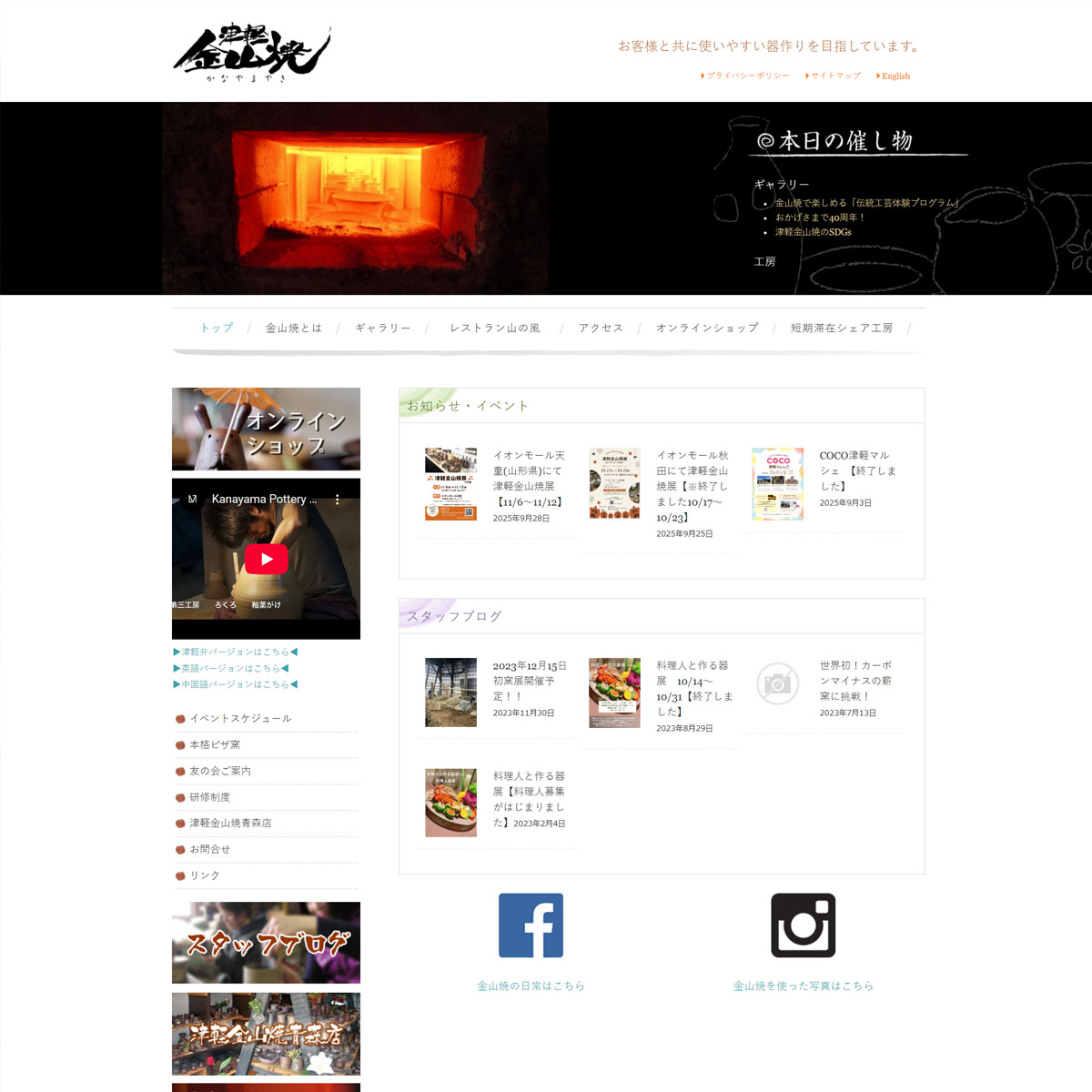
ここが推し!
釉薬を一切使わず、土と炎だけで焼き上げる「焼き締め」の器。その実力は、ビールを注げばクリーミーな泡が立ち、コーヒーを淹れれば角が取れてまろやかになるほど!「水がおいしくなる」という評判は伊達じゃありません。素朴で温かみのある肌触りは手に馴染みやすく、使い込むほどに艶が出て育っていく過程も楽しめる、一生モノの相棒です。
PROFILE 企業・工房について
津軽金山焼の始まりは、地元の資源を活かしたものづくりでした。昭和60年頃、金山の大溜池に眠っていた粘土を、薪窯で焼き締める陶器の原料として活用することを決めたことが出発点とされています。以降、試行錯誤を重ねながら登り窯を築き、津軽の土と赤松だけで器を焼き上げる技術を磨いてきました。
焼き締めの器は、釉薬を使わないぶん、土の質や焼成の条件がそのまま表情に現れます。窯場では、5つの成形技術(ろくろ、機械ろくろ、流し鋳込み、圧力鋳込み、たたら)を使い分け、器の用途やサイズに応じて最適な方法で制作。焼成では窯の位置や炎の通り道を見極めながら、狙い通りの窯変を生かしたうつわづくりを行っています。
なかでも注目を集めているのが「水をきれいにする器」です。ウォーターボトルやカップを使った試験では、水道水を一晩入れておくだけで鉄分やカルシウムが検出されることが明らかになり、水やお茶、お酒がまろやかになると評判に。こうした機能性と、焼き締めならではの味わい深い表情の両立が、金山焼の大きな特徴となっています。
現在、津軽金山焼はギャラリー和土WANDOやレストラン山の風、オンラインショップ、各地での企画展やコラボレーションを通じて、多くのファンを獲得しています。使い捨てではなく、使うほどに風合いが増し、水や植物、料理とともに育っていく器を届けること。津軽の土と炎の仕事を通して、暮らしを少し豊かにすること。それが、窯元とスタッフが大切にしている金山焼の姿です。
津軽の土と赤松の炎が生む、釉薬を使わない焼締陶器
津軽金山焼の素地は、金山の大溜池の底に堆積した良質な粘土。燃料には山林の赤松を使い、釉薬を一切使わずに薪窯で高温焼成することで、土の成分と灰が溶け合った自然釉や桟切り、灰かぶりなど、多彩な表情が生まれます。同じ形の器でもひとつとして同じ景色はなく、窯の位置や炎の流れによってオンリーワンのうつわに育ちます。
水をきれいにし、味わいも変える「おいしい水」の器
焼き締めの器は通気性に優れ、津軽金山焼では特に「水をきれいにする力」を活かしたウォーターポットや石ころ、ウォーターボトルが人気です。土と薪窯で生まれた器から鉄分やカルシウムが溶け出し、水やお茶、お酒がまろやかに感じられるという検査結果や口コミも。冷蔵庫のドアポケットに収まるよう設計されたボトルなど、日々の習慣として取り入れやすいかたちで提案しています。
食卓まわりからインテリア、ピザ窯まで広がるラインナップ
金山焼の主力は毎日の食卓で使える器です。皿や鉢、ビアカップ・酒器、珈琲カップ、飯碗から、花器・オブジェ、ピザ窯や手洗い鉢、植木鉢まで、暮らしのさまざまなシーンを彩るアイテムを幅広く展開。ギャラリー和土WANDOでは記念品コーナーや釉薬コーナー、津軽塗とのコラボなど、用途別・テーマ別に作品が並び、楽しみながら器選びができます。
窯元・作家・スタッフがつくる「開かれた窯場」
敷地内には登り窯や工房を中心に、展示館、レストラン、短期滞在シェア工房などがあり、訪れる人が金山焼の世界観を丸ごと体験できる場になっています。窯元の一品物を集めた松風ギャラリーや、陶芸教室講師の作品コーナー、女性作家による小物のショップなど、多様な作り手が関わる「開かれた窯場」として、新しい金山焼の楽しみ方を発信しています。
LINKS 公式リンク / SNS
- 公式サイト http://kanayamayaki.com/
- オンラインショップ https://store.shopping.yahoo.co.jp/kanayamayaki/
- お問い合わせフォーム mailto:info@kanayamayaki.com
- X(公式) https://x.com/kanayamayaki
- 津軽金山焼 公式サイト(トップページ) http://kanayamayaki.com/
- 津軽金山焼オンラインショップ(Yahoo!ショッピング) https://store.shopping.yahoo.co.jp/kanayamayaki/
- 津軽金山焼|青森県公式観光情報サイト https://aomori-tourism.com/spot/detail_307.html
- 伝統工芸で暮らしをもっと豊かに。津軽金山焼紹介記事 https://loconohoshi.com/monodukuri/kanayamayaki/
- 津軽金山焼 公式Facebookページ https://www.facebook.com/kanayamayaki/

